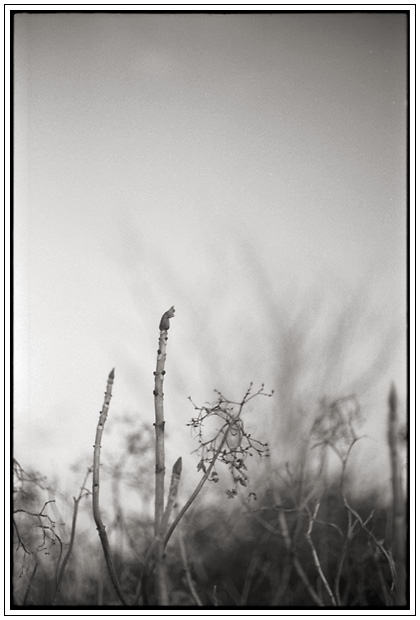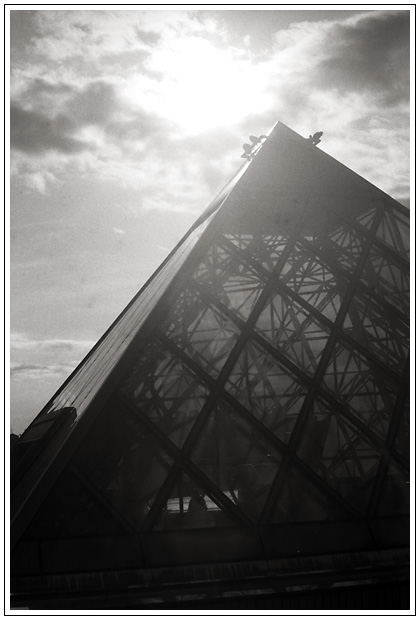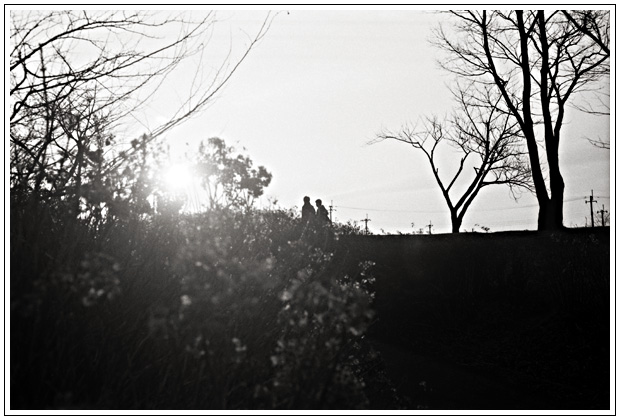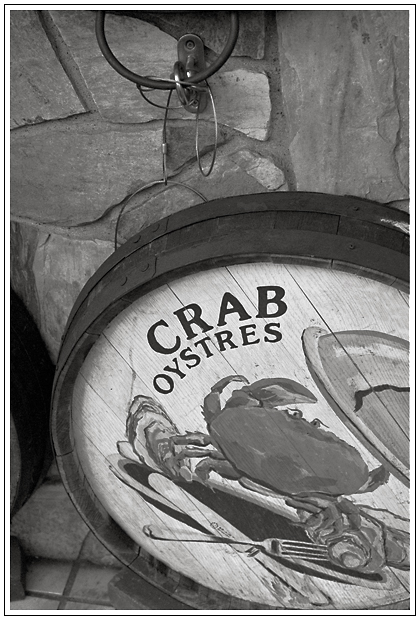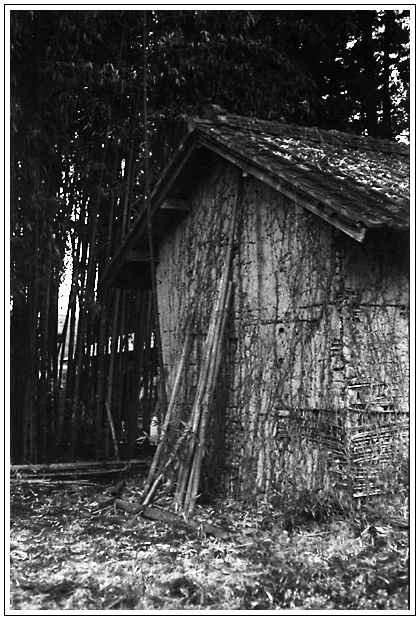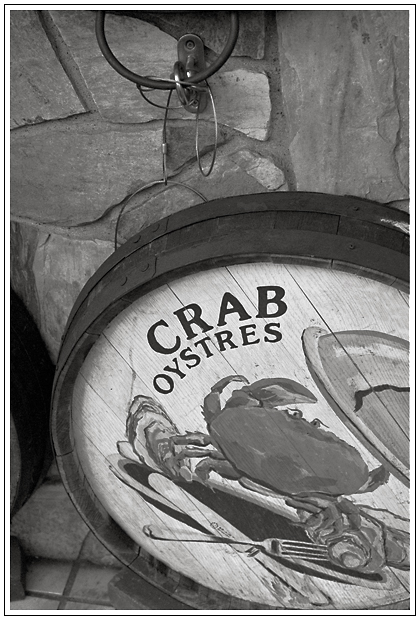
仕事がちょっとごたごたしていてエントリーがストップしていました。
さて,本日帰宅してみるとちょっとした段ボール箱が。
持ってみるとずしりと重い。
これは,日曜日に購入したスピーカースタンド。
正月にハイビジョンレコーダーを購入し,BSハイビジョンで録画した音楽番組を見ていたのです。
番組は葉加瀬太郎の10周年記念ライブ。
でも,今ひとつ主役のヴァイオリンの音がはっきり聞こえてこない。
周りのバッキングの楽器の音に埋もれてしまっていたんです。
でも,そんなものなのかなぁ,と最初は思っていました。
しばらくして,以前から持っていた古いアンプにハイビジョンレコーダーから音を流してみたらどうなるかな,と思いついたわけです。
BOSEの101MMというこれまたかなり古いスピーカー。
いったんはコンピュータにつないでいたのですが,再度アンプにつなぎ直して音を出してみました。
するとどうでしょう,ヴァイオリンの音がはっきり聞こえるじゃないですか。
途中からヴァイオリンのデュオの演奏になったのですが,2台のヴァイオリンの音が出てくる位置が分離してきただけでなく,ヴァイオリンの持つ音の違いまで分かってきたんです。
これにはびっくりでした。と同時に,なんて今まで勿体ないことをしていたのかとアンプもスピーカーも眠らせていたことを後悔しました。
ただ,まだちょっとだけ問題がありました。
BOSEの101MMはそれまでリビングの床に転がしていたんです。
床に置いたままで聞くとやっぱりあんまりいい音には聞こえてこないんですね。
テレビ台などの上にスピーカーをのせてみたらぐっと空間が広がって聞こえたんです。
そう,これはもうすぴーかースタンドを購入するしかない!!!(^。^)
と言うわけで,日曜日にヨドバシカメラに行ってみました。
ところが101MM用のフロアスタンドってあまり無いんですねぇ。
店員さんも今ひとつはっきりしなくって・・・。
ちょっとあきらめモードになったのですが,市内の老舗のオーディオ専門店に行ってみることにしました。
店員さんは流石にいろいろと詳しくて,勧められたのがハヤミのスピーカースタンドSB-302。
これならば,次にスピーカーをグレードアップしたときにも使えると勧められて,思い切って購入に至ったわけです。
思えば,スピーカースタンドは大学の頃からの憧れだったかもしれません。
大学3年の頃にオーディオに目覚め,バイトをして昼食代を削って4年の春に一式を買いました。
と言っても,アンプとスピーカー,レコードプレーヤーのみでしたが。
その時,予算が無くて,スピーカースタンドが買えず,ホームセンターで風呂用の木の椅子を買ってきてごまかしていたんですねぇ。
まぁ,当時はスタンドで音が変わるなんて事をあまり信じていなかったので,まぁいいかと思っていました。
でも,その当時から,スピーカースタンドは欲しいアイテムの一つだったんです。
帰宅後早速スタンドを組み立て,スピーカーを置いてみました。
知っていらっしゃる方は分かるとおりBOSEの101MMっていうスピーカーは本当に小さなスピーカーです。
スタンドに乗っけた程度でそんなに大きな変化は無いだろうと思っていたのですが・・・。
いやぁ,劇的な変化でした。
テレビ台の端っこに乗せたときに感じた何となく中音域に感じた癖のようなものがなくなり,
すっきりと音が広がっていくんです。
しかも,ちゃんと楽器が定位している。
BOSE特有の小音量なのに部屋の中にしっかり聞こえてくる音の響きが実感できました。
思わず,これまたしばらく眠っていたレコードプレーヤーに,お気に入りのLPをのせて一枚聞いてしまいました。
聞いた一枚はグレン・グールドのデビューアルバム,ゴールドベルグ変奏曲。
録音は1950年代と言うことで半世紀前の演奏なのですが,うーん,いい音だ(^。^)。
楽しみが増えましたねぇ。
ちょっと低域が物足りない感じがするので,ウーハーを購入するか,はたまたメインのスピーカーをグレードアップするか(^^ゞ。
しばらく,はまってしまいそうです。
Camera : Leica M4-2
Lens : Leica Summicron 50mm F2
FIlm : Ilford XP2 400